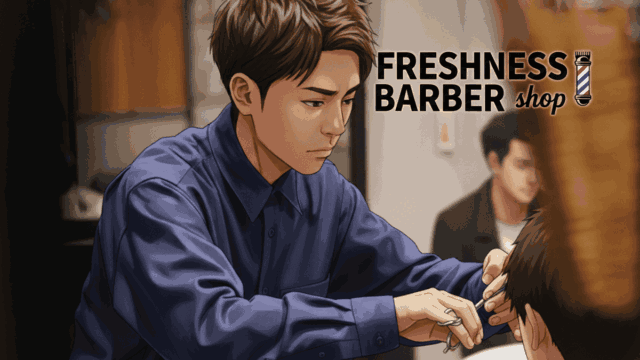理髪店の昔の言い方とは?「床屋」の由来と、時代を超えて受け継がれる心
私たちが今日、当たり前のように使っている「理髪店」という言葉。しかし、その歴史を遡ると、時代と共に様々な呼び名で親しまれてきたことがわかります。「昔の言い方は何だろう?」という、その素朴な疑問は、日本の男性の身だしなみの文化を紐解く、興味深い旅の始まりです。この記事では、理髪店の昔の言い方とその由来について、詳しくご紹介いたします。
最も代表的な昔の言い方「床屋(とこや)」
「理髪店」の昔の言い方として、最も代表的で、今なお多くの方々に親しまれているのが「床屋(とこや)」という言葉です。どこか温かく、地域に根差した親しみやすい響きを持つこの言葉は、単に髪を切る場所というだけでなく、人々が集い、心を通わせる、そんな古き良き日本の情景を思い起こさせます。
「床屋」の語源となった「髪結床(かみゆいどこ)」
では、その「床屋」という言葉は、どこから来たのでしょうか。そのルーツは、男性が「ちょんまげ」を結っていた、江戸時代にまで遡ります。当時、人々の髪を結う職人は「髪結(かみゆい)」と呼ばれていました。彼らが仕事をしていた、一段高い板張りの作業場や、簡易な店舗のことを「床店(とこみせ)」と呼び、そこから「髪結床(かみゆいどこ)」という名称が生まれました。この「髪結床」こそが、「床屋」の直接の語源であると言われています。そして、この場所は単に髪を結うだけでなく、町の人々が集まり、情報交換をする社交場としての役割も担っていたのです。
時代と共に変化してきた、その他の呼び名
明治時代に入り、ちょんまげを切り落とす「断髪令」が出されると、西洋式の短髪スタイルが主流となり、髪結床は近代的な「理髪店」へと姿を変えていきました。「理容」という、より専門的な言葉が使われるようになり、衛生管理の行き届いた空間で、専門家がサービスを提供するという、現代に繋がるイメージが定着しました。さらに近年では、「バーバー」や「メンズヘアサロン」といった、新しい呼び名も生まれています。
呼び名は変われど、変わらない理容師の役割
「髪結床」から「床屋」、そして「理髪店」へ。時代と共にその呼び名やヘアスタイルは大きく変化してきましたが、その根底に流れる本質的な役割は、今も昔も何一つ変わっていません。それは、お客様の身だしなみを整え、容姿を清潔にすることで、その方の心に自信と活力を与えるお手伝いをさせていただく、ということです。江戸時代の髪結床が地域の社交場であったように、現代の理髪店もまた、お客様が日々の喧騒から離れ、心からリフレッシュできる、安らぎの場所でありたいと願っています。
誠実な理容師が受け継ぐ、昔ながらの心
私たち誠実な理容師は、こうした歴史の変遷の中で、昔ながらの「床屋」が持っていた温かい心と、「理髪店」が培ってきた専門的な技術の両方を受け継ぐことを誇りに思っています。呼び方は変われども、お客様一人ひとりと真摯に向き合い、信頼関係を築き、その方の人生に寄り添うパートナーでありたい。その想いこそ、時代を超えて受け継がれるべき、理容師の魂であると信じております。