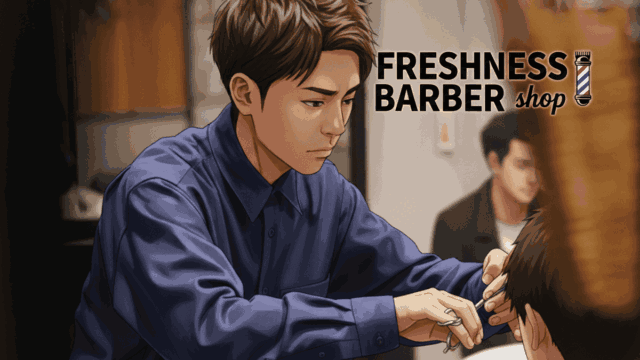「髪をすく」時、何センチ切る?プロが操る、長さではない”深さ”と”量”の世界
バーバーサロン(理容室)で髪を梳いてもらっている時、自分の髪が一体、今、何センチくらい短くなっているのだろう?」と、ふと疑問に思われたことはございませんか。全体の長さを決めるカットとは違い、髪を梳く施術は、その変化が目に見えにくく、どのくらい量を調整したのかが分かりにくいものです。実は、私たちプロの理容師が「髪を梳く」時に考えているのは、皆様が想像するような、単純な「何センチ」という長さの単位だけではございません。そこには、お客様のヘアスタイルを立体的に、そして機能的に創り上げるための、より複雑で、より重要な基準が存在するのです。
「梳く」とは、「長さを変える」技術ではない
まず、最も大切な前提として、「髪を梳く」という技術の主な目的は、ヘアスタイル全体の長さを変えることではない、という点をご理解ください。その真の目的は、あくまでお客様の髪全体の長さを維持したまま、その内側に働きかけ、髪の「量」や「質感」を繊細に調整することにあります。そのため、「何センチ切る」という、長さを基準とした発想とは、根本的に異なっているのです。
プロが操る、3つの「ものさし」
では、私たちは「何センチ」という単位の代わりに、どのような「ものさし」を基準に、髪を梳いているのでしょうか。私たちの頭の中には、少なくとも三つの、異なるものさしが存在します。
① 梳く「深さ」:根元から、何センチの位置に入れるか?
一つ目は、髪の根元から、どのくらいの「深さ」にハサミを入れるか、という基準です。例えば、根元近くを梳くと、短い毛が内側から髪全体を押し上げ、意図的にボリュームを生み出す効果があります。逆に、毛先だけを梳けば、スタイルに自然で軽やかな動きが生まれます。私たちは、お客様の髪質や創り出したいスタイルに応じて、根元から何センチ離れた、最も効果的な「深さ」を、ミリ単位で的確に判断しています。
② 梳く「場所」:どの部分を、重点的に梳くか?
二つ目は、ヘアスタイルのどの「場所」を、重点的に梳くか、という基準です。例えば、ボリュームをすっきりと抑えたいサイド(ハチ周り)の内側や、動きを出したいトップの部分、あるいは、刈り上げ部分と自然に馴染ませたい襟足など、目的によってアプローチすべき「場所」は全く変わってきます。これは、お客様の骨格を最も美しく見せるための、非常に重要な判断です。
③ 梳く「量(%)」:どのくらいの割合で、髪を間引くか?
そして三つ目が、どのくらいの「量」を減らすか、という基準です。私たちが使うすきバサミには、一度ハサミを入れることで、その毛束の15%の量が減るもの、あるいは30%減るものなど、実に様々な種類がございます。お客様の元々の毛量や、お求めになる軽さのイメージに合わせて、最適な「割合(%)」で髪を間引くことができる道具を、的確に選択しているのです。
「何センチ梳いてください」というオーダーについて
ここまでご説明させていただいた通り、プロの「梳き」の仕事は、単純なセンチメートルでは測れない、非常に複雑な要素で成り立っています。そのため、お客様から「〇センチくらい梳いてください」とご注文いただくよりも、「指でつまんだ時に、このくらいの軽さになるように」「今の半分くらいの量になるイメージで」といった、感覚的な表現や、理想のスタイルの写真をお見せいただく方が、実は私たちとお客様との間で、完成イメージの共有がしやすいのです。
誠実な理容師は、お客様との「感覚の共有」を大切にする
究極的には、ヘアスタイルの良し悪しは、「何センチ切ったか」という数字ではなく、お客様ご自身が「ちょうど良い」と感じられるかどうか、という、その感覚的な部分で決まります。私たち誠実な理容師の仕事は、専門知識を一方的に押し付けることではございません。施術の途中で「このくらいの軽さで、一度触ってみていただけますか?」とお客様にお声がけするなど、お客様との「感覚の共有」を何よりも大切にしながら、一歩ずつ、共にゴールを目指していくことです。
「髪を梳く」という技術は、単純な「長さ」の世界ではなく、髪の「深さ」「場所」「量」という三つの要素を自在に操る、三次元的なデザイン行為です。数字では測ることのできない、あなたのためだけの「最高の心地よさ」。それを形にすることこそが、私たちの仕事です。ぜひ一度、感覚を共有しながらスタイルを創り上げる、オーダーメイドのヘアデザインを、私たちのサロンでご体験ください。